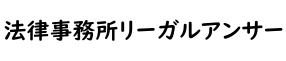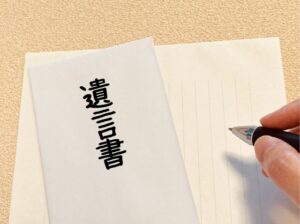遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言を作成した後、「紛失や改ざんが心配」「相続人がスムーズに遺言を確認できるようにしたい」と思われる方も多いでしょう。そこで利用できるのが 法務省の「自筆証書遺言書保管制度」です。
この制度を利用すると、法務局が遺言書の原本を厳重に保管し、紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減できます。さらに、相続発生後は家庭裁判所での検認が不要となり、相続手続きが円滑に進みます。
本記事では、法務省の公式サイト(法務省:自筆証書遺言書保管制度)をもとに、制度の利用方法や手続きの流れについてわかりやすく整理してご説明します。実際の申請にあたっては、必ず最新の情報を確認のうえ、お近くの法務局や法務省のWebサイトなどで詳細をご確認ください。
<利用手続きの流れ>
1. 遺言書の作成
- 遺言書は全文を自書し、 日付・氏名・押印を必ず記入します。
- A4用紙を使用し、片面のみに記載します。
- 財産目録はパソコン作成が可能ですが、各ページに署名・押印が必要です。
- 余白やページ番号の記載ルールを守ります(例:「1/2」「2/2」)。
※保管申請時に、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するか、遺言書保管官の外形的なチェックがされますが、内容の有効性や法律的妥当性を精査するものではありません。
2. 必要書類の準備
- 作成した自筆証書遺言
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 住民票(本籍記載あり)
- 申請書(法務省HPでダウンロード可)
- 手数料 3,900円分の収入印紙
- 印鑑
3. 予約・申請手続き
- 管轄の法務局を確認し、事前予約を行います。
- 予約日に法務局へ出向き、必要書類を提出します。
- 保管申請が受理されると、法務局が原本を保管し、画像データとしても長期間管理されます。
- 保管証が発行されます(再発行不可のため、大切に保管してください)。
<保管後の取り扱い>
1. 遺言書の変更・撤回
- 変更したい場合は、一度撤回して新たに保管申請が必要です。
- 撤回する場合は、法務局で「遺言書の撤回申請」を行い、返却してもらいます。
2. 相続発生後の取り扱い
- 相続人や受遺者は、遺言者の死亡を証明する書類を提出し、遺言書の閲覧や証明書の交付を請求できます。
- 相続人のうち一人が請求すると他の相続人にも遺言書が保管されている通知が届きます。
- 家庭裁判所での検認手続きが不要となり、滞りなく遺産分割手続きを進めることができます。
<制度を利用する際の注意点>
- 内容面の有効性
- 利用できる遺言書の種類
- 記載の形式要件
- 遺言書の原本は返却不可
保管制度では、遺言書の法律的な有効性・遺産分配方法の妥当性まではチェックされません。内容に不備があると、結果的に無効になる場合もありえます。専門家に相談するなど、作成段階で内容を十分に確認することが重要です。
「自筆証書遺言」のみが対象です。公正証書遺言や秘密証書遺言は本制度では取り扱えません。
自書・日付・氏名・押印などの形式要件を欠いていると、法務局で保管を断られることがありますのでご注意ください。
いったん法務局に保管されると、遺言者が自ら保管を取り下げる(撤回する)手続きをしない限り、原本は返却されません。
まとめ:弁護士とともに確実な遺言を
遺言書保管制度を活用することで、安全に遺言を残すことができます。ただし、 遺言の内容が法律的に有効かどうかまではチェックされません。遺言の文言が曖昧だったり、法律的に無効な内容が含まれたりしていると、せっかくの遺言が無効になるリスクもあります。「自分の意思を確実に伝えたい」「相続人のトラブルを防ぎたい」とお考えの場合には、弁護士に相談しながら遺言を作成することをおすすめします。
当事務所では、遺言の作成から保管手続きまで、しっかりとサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。