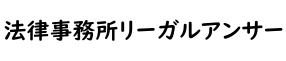自筆証書遺言の作成方法とは?
自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書し、押印することで法的効力を持つ遺言です(民法968条1項)。しかし、書き方に不備があると無効になるリスクがあるため、正しい手順で作成することが重要です。本記事では、自筆証書遺言の作成方法と注意点を解説し、特に不動産の相続に関して専門家に相談するメリットをご紹介します。
1.自筆証書遺言の基本ルール
- 遺言書の本文はすべて(内容・日付・氏名)を自分で手書きして作成してください。字が書けないという方は、公正証書で遺言書を作成することになります。
- 「すべて自書」が基本ですが、法改正により一部要件が緩和され、「相続財産の目録」については、自書によらない方法で作成が可能となりました(民法968条2項参照)。その場合でも、各ページに署名と押印が必要になります。
- ボールペンや万年筆など、消えない筆記用具を使用し、フリクションペンなどの消せるペンは避けましょう。
<記載すべき内容>
- 遺言の全文: 自分の意思を正確に表現し、誤解を招かないよう簡潔に記載します。
- 日付:「2025年3月10日」など、年月日が特定できる形式で記載してください。
- 氏名: 戸籍上の氏名を自書してください。
- 押印: 実印が望ましいですが、認印でも法的には有効です。スタンプ印やいわゆるシャチハタ印は避けてください。
<不動産や財産の記載方法>
- 不動産については登記事項証明書を参考に、土地は「所在・地番・地目及び地積」を記載し、建物は「所在・家屋番号・種類・構造及び床面積」を記載します。
- 預貯金は「銀行名・支店名・預金種(貯金種)・口座番号(記号番号)・口座名義人」など、株式も、非上場のものであれば「会社名、本店、株式の種類、株式数」などを記載し、上場株の場合には、口座のある証券会社名・支店名・口座番号なども詳細に記載しておくとよいでしょう。
- なお、自書によらない「相続財産の目録」として、上記内容をパソコンで作成したものでもよく、不動産であれば登記事項証明書の写し、預貯金通帳の写し(銀行名・支店名・口座名義・口座番号等が分かる頁)でも構いません。
<遺言書の管理>
- 複数ページの場合: ページ番号(例:「1/3、2/3、3/3」)を記載します。財産目録を作成した時も、遺言書本文とつながるように通し番号を振ります。ホチキス留めや契印をして改ざんを防ぎましょう。
- 修正や訂正の方法:訂正する文字を二重線で消して訂正印を押し、訂正した部分が分かるように修正内容を明記してください。また訂正した行の近くの余白に、訂正した箇所が分かるように示した上で、削除や加えた文字数(例:2文字削除3時追加)を付記して署名します。
- 民法968条3項で定められた訂正方法に従わないと遺言書の効力に影響するため、修正が多い場合は書き直しをおすすめします。また公正証書で遺言を作成することもご検討ください。
2.遺言書の保管方法
- 自宅で保管する場合は、紛失や改ざんのリスクがあるため注意が必要です。また開封前に改定裁判所での「検認」も受けなければなりません。検認を受けずに遺言書を開封すると、開封者には過料が課される可能性があるため、遺言書の封筒には「必ず検認を受けるように」と記載しておくことがリスク回避となります。
- 法務局の自筆証書遺言保管制度を活用すると、安全に保管でき、相続時の発見や確認が容易になります。(自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、用紙や記入方法にさらに要件が加わります。法務局のホームページをご参照ください。)
- 弁護士や信頼できる家族に預ける方法も有効ですが、内容を事前に弁護士に確認してもらうとより安心です。
3.不動産に関する遺言の注意点と弁護士の重要性
不動産は相続において特にトラブルになりやすい財産の一つです。登記情報の不備や、複数の相続人が関与するケースでは、後々の紛争につながる可能性があります。不動産を遺言に含める際のポイントは、上記で記載した「登記情報を正確に記載し、地番・家屋番号を誤らないようにする」ことのほか、「共有名義になっている場合は相続人間での権利関係を明確にする」ことや、「不動産の評価額を確認し、公平な分割方法を考慮する」ことも重要です。
このように、単に登記情報を記載するだけでなく、複雑になりがちな不動産相続は、不動産鑑定士資格を持つ弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けることができます。
- 適正な不動産評価を基にした公平な分割方法の提案が可能
- 相続税対策を考慮した遺言作成ができる
- 複雑な不動産取引や登記の手続きにも対応可能
- 遺産分割協議が難航した場合の法的サポートを受けられる
特に、不動産の評価額が高額な場合や、複数の相続人が絡むケースでは、弁護士の専門知識と不動産鑑定士の視点の両方を活かしたアドバイスが、スムーズな相続手続きに直結します。
4.まとめ
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、特に不動産を含む場合は、記載ミスや曖昧な表現が原因で無効になる可能性があるため、慎重に作成することが重要です。また、相続財産に不動産が含まれている場合、適切な内容で遺言を作成するためには、不動産案件に精通した弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
当事務所では、不動産鑑定士の資格をもつ弁護士が、遺言作成から相続手続きまで対応いたします。不動産の相続に関する不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。